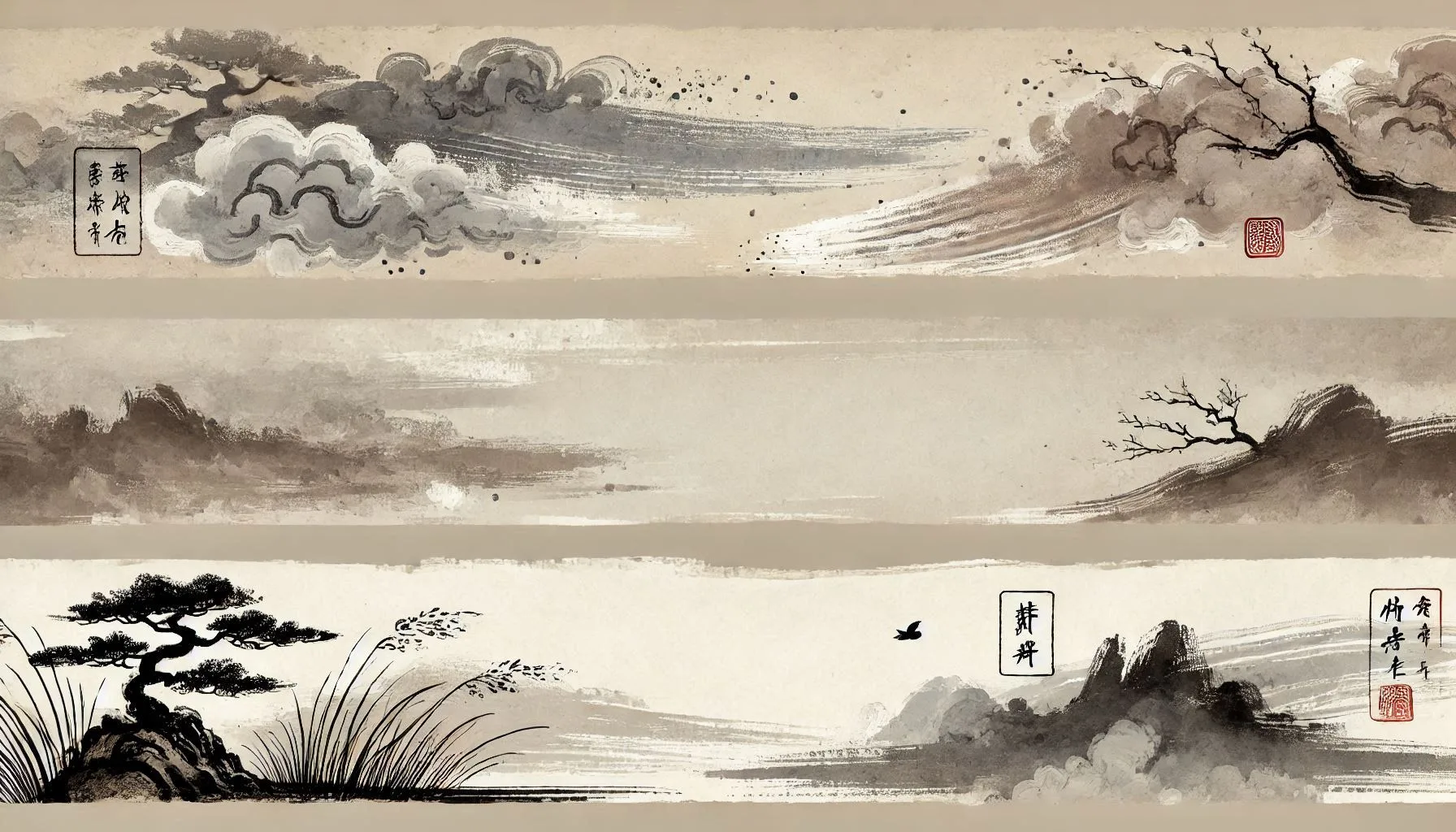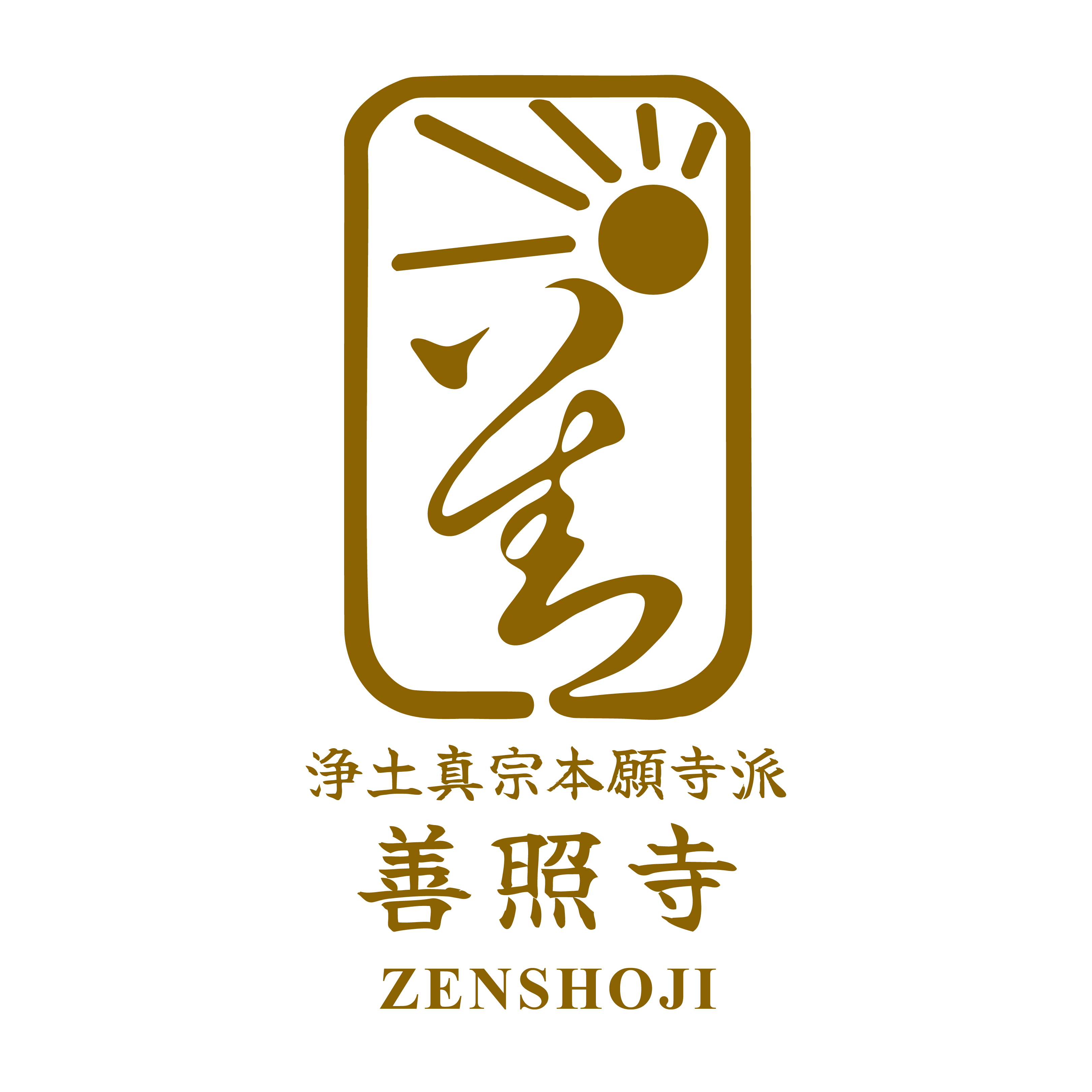真の智慧は
そのまま大悲でもある―上山 大峻『平等への視座 -対談・歴史的課題と教団-』
(梯 實圓×上山 大峻 対談)
法語の意味
仏教で説かれる「智慧(ちえ)」とは、単なる知識や頭の良さを指すものではありません。自分中心の考えや価値観を超えて、ものごとの本質をありのままに見つめる力こそが仏教で言う「智慧」です。
そして、その智慧には、必ず温かい心が伴います。それは「大悲」と呼ばれ、人や世界を分け隔てなく包み込む大きな慈悲を表します。
つまり、正しくものごとを見つめる真の智慧は、同時に「すべての人をどうか救いたい」という限りない思いやり(大悲)の姿そのものでもあるのです。
副住職のお話
春を迎え、寒さも和らぎ、桜のつぼみがほころび始める季節となりました。新しい環境での生活が始まる方もいらっしゃるでしょうし、年度末・年度始めの慌ただしさで落ち着かない方も多いかと思います。そんな三月に、あらためて「真の智慧は そのまま大悲でもある」という法語に目を向けてみましょう。
私たちは普段、物事を判断するとき、「自分にとって損か得か」「好きか嫌いか」という基準にとらわれがちです。しかし、仏さまの目から見た「真の智慧」とは、そうした自分中心の思考を超え、相手や周囲の事情にも心を配りながら、ものごとを正しく見抜く力をいいます。さらに、その智慧は、他者への分け隔てないまなざしや思いやりである、「大悲」と一体であると説かれます。すなわち、「私さえ良ければ」という考えを離れ、誰かを思いやる心が深まるほど、真実を見つめる智慧もはたらいてくるのです。
たとえば、新年度の職場や学校など、環境が変わる場面では、相手との意思疎通が難しかったり、人間関係がギクシャクしてしまったりすることがあります。そんなとき、「自分は悪くないのに、どうしてこんな目に合うのだろう」「あの人のせいで、私ばかりが大変だ」という感情が先立つかもしれません。
しかし、そこでもし「相手にも事情があるかもしれない」「自分に見えていないだけで、相手の悩みや苦しみがあるのではないか」と想像できたらどうでしょうか。これは、相手の立場を慮り、相手を受けとめる姿勢を持とうとする「大悲」の心に通じるでしょう。すると、「もしかしたら、自分の言動にも相手を傷つける要素があったのかもしれない」という気づきが生まれたり、「ただ責め立てるのではなく、助け合うことが必要かもしれない」と感じられたりします。ここに、他者を理解しようとする「智慧」と、それを支える「大悲」のはたらきが育まれていくのです。
もちろん、理屈では分かっていても、実際には感情が先走り、「なぜあの人はわかってくれないのだろう」と怒りや苛立ちを覚えることもあるでしょう。そうした「どうにもならない自分の姿」を正直に見つめていくこと。これもまた仏教の「智慧」と言えます。「自分にできること」「相手にゆだねるしかないこと」を見極めながら、互いを思いやる心を育むとき、私たちは少しずつ「大悲」の世界に近づいていくのではないでしょうか。
おわりに
「真の智慧は そのまま大悲でもある」という三月の法語は、私たちの身近な人間関係や社会の出来事の中で、相手を思いやる心こそが本質を見通す智慧に通じている、という大切な事実を示しています。私たちが日常でぶつかる問題や行き違いも、仏さまの教えを通してみると違って見えてきます。
仏さまの視点で自分や相手を見つめることで、今までは「理解できない」と思っていたことにも、新しい光が差し込んでくるかもしれません。3月はお彼岸の時節でございます。ぜひ、お寺にもお越しいただき、ご一緒にお念仏を称えながら、春のスタートを穏やかに迎えていきましょう。皆様のご参詣を心よりお待ち申し上げております。
※ この「今月の法語」は毎月更新いたします。