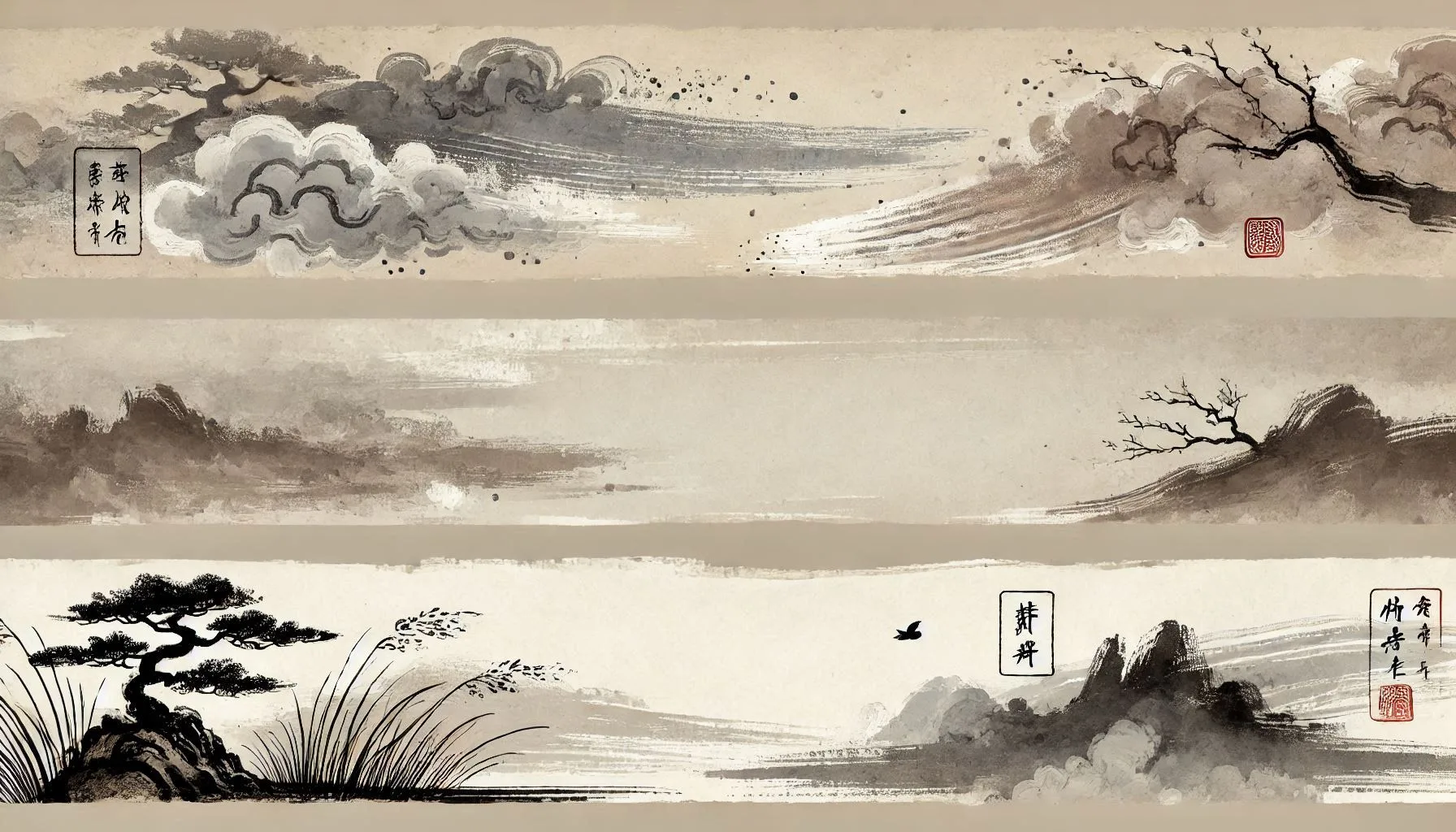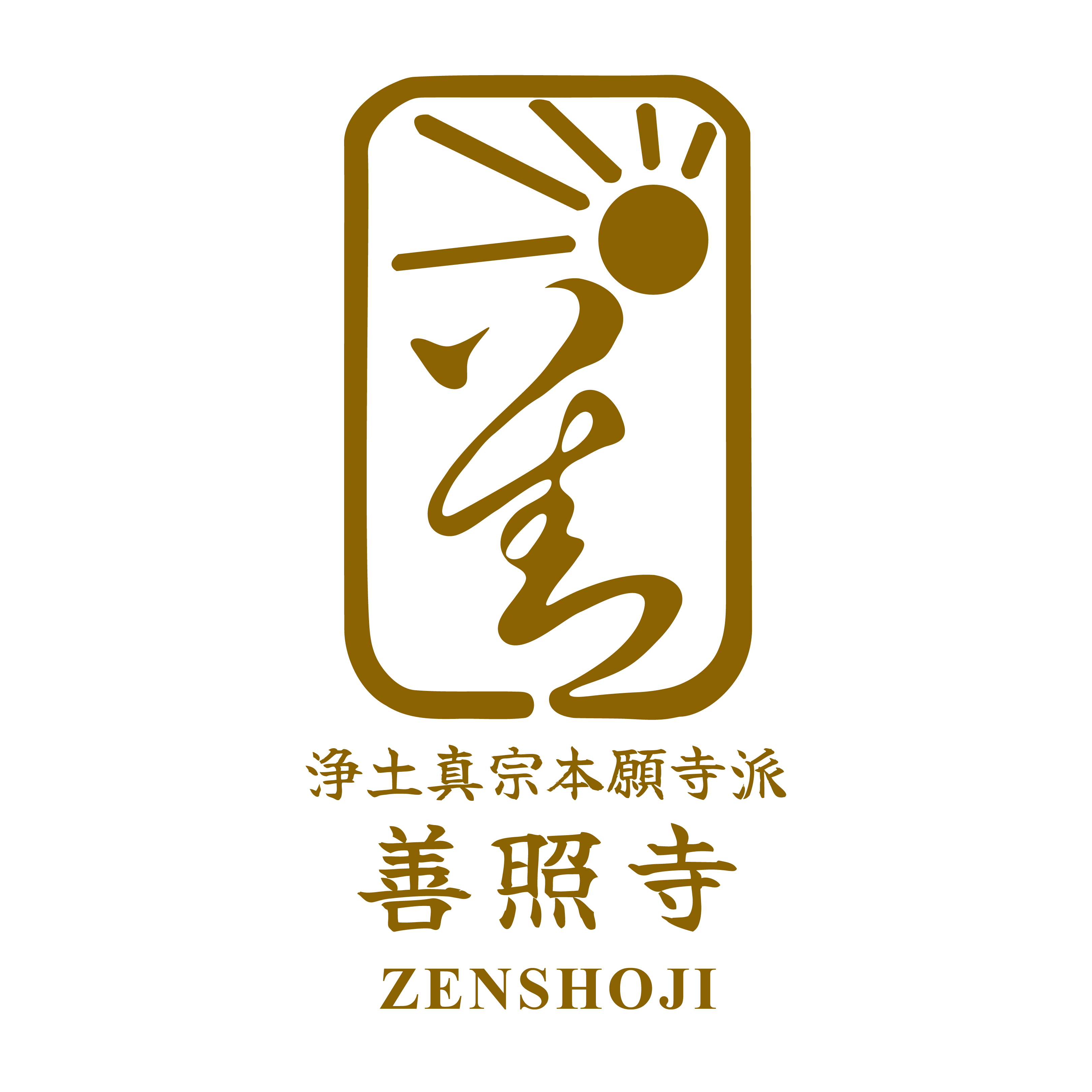浄土真宗は、鎌倉時代の承元元年(1207)に親鸞聖人によって明らかにされた仏教の一派です。インドで説かれた阿弥陀如来の本願による救いの教えが、中国を経て日本に伝わる長い歴史の中で、すべての人々を極楽浄土へ往生させたいという願いとともに、大切に受け継がれてきました。
教えの源流
インドでは、はるか昔に龍樹(りゅうじゅ)菩薩が念仏による救いを示されました。これは、誰もが実践できる方法として「南無阿弥陀仏」を称え、阿弥陀如来のお力によって救われるという易行の教えでした。
その後、この教えは中国へと伝わり、曇鸞(どんらん)大師や道綽(どうしゃく)禅師、善導(ぜんどう)大師などの高僧方によって体系づけられていきます。なかでも善導大師は念仏の教えを広く説かれ、日本の浄土教に大きな影響を与えました。
日本への伝来
日本では、聖徳太子が仏教を国の柱として重んじたことをきっかけに、時代とともにさまざまな宗派の仏教が伝わりました。
鎌倉時代に入ると、法然上人が浄土宗を開かれ、「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」の教えを説かれます。これは、学問や厳しい修行ではなく、南無阿弥陀仏とお念仏を称えることによって、誰もが阿弥陀如来のお慈悲にあずかれるという、革新的な教えでした。
それまでの仏教は、どちらかといえば学問のある人や、修行を重ねた人のためのものでした。しかし法然上人は、誰もが実践できる念仏の教えを広められたのです。
親鸞聖人と浄土真宗
法然上人の弟子である親鸞聖人は、さらに深く「他力本願」の教えを明らかにされます。それは、自分の力による悟りではなく、阿弥陀如来のお力によって救われるという教えです。
親鸞聖人は流罪や関東での布教を通じて、多くの人々と出会い、阿弥陀如来のお慈悲をより広く、より深く伝えられました。そのみ教えが、後に浄土真宗として大きく花開くことになります。
教えの広がり
親鸞聖人の御往生後、真宗の教えは門弟たちによって各地に伝えられました。室町時代になると、蓮如上人が時代の人々にも分かりやすい言葉でお念仏のみ教えを説かれ、多くの人々の心に響く「御文章(ごぶんしょう)」を残されます。これによって教団は急速に発展し、浄土真宗は全国に広がっていきました。
本願寺の確立
こうした流れの中で、本願寺は親鸞聖人の御影堂(ごえいどう)を起源として建立されました。八代宗主の蓮如上人の時代に、現在の浄土真宗本願寺派の基礎が築かれ、多くの寺院が整えられていきます。その後も歴代のご門主によって親鸞聖人の教えが護持され、本願寺は多くの人々を阿弥陀如来のお念仏へといざなう拠点としての役割を果たしてきました。
現代に生きる教え
明治維新以降の大きな社会変化の中でも、本願寺は親鸞聖人のみ教えを大切に守り続けてきました。
「南無阿弥陀仏」のお念仏は、今なお多くの人々の心の支えとなっています。それは、時代や社会が変わっても、人々の救いを願う阿弥陀如来様のお心は変わることがないからです。
浄土真宗の歴史は、親鸞聖人の教えを中心に、時代とともに歩みながら、人々の救いを願い続けてきた歩みといえます。その教えは、今日も変わることなく、私たちの心に語りかけています。